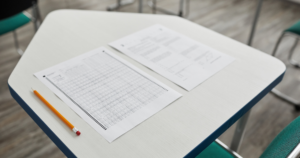高所作業車を運転するには資格が必要ですが、いざ受講しようとすると
- 「自分の免許や資格でどのコースを選べばいいのか分からない」
- 「受講料金はいくらぐらいかかるのか」
- 「申込から支払いまでの流れが複雑そう」
と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では高所作業車運転特別教育(10m未満)の受講資格・費用・申込方法を整理しました。読後には、自分に合った受講プランを見極め、スムーズに資格取得へ進めるようになります。

高所作業車特別教育とは?

建設現場や電気工事、通信設備の設置などで使用される高所作業車は、作業効率を大きく高める便利な機械です。しかしその一方で、墜落や転倒といった重大事故につながるリスクも抱えています。そのため労働安全衛生法に基づき、作業床高さが10m未満の高所作業車を運転する場合には「高所作業車運転特別教育」の修了が義務付けられています。
この特別教育は、技能講習と比べると受講条件が緩やかで、普通自動車免許がなくても受講できます。基本的に18歳以上であれば誰でも受講可能であり、建設業や電気工事業に従事する新入社員、転職を目指す未経験者にとっても門戸が広く開かれています。
また、特別教育の目的は「安全に操作できる知識と基本技能を身につける」であり、修了すれば高所作業車の運転業務に従事することが可能になります。資格を持たずに作業を行えば事業者が法令違反となるため、現場に出る前に必ず修了証を取得することが第一歩です。
高所作業車特別教育の費用相場
一般的な受講料の目安
全国の安全衛生教育センターや民間の教習機関における受講料の相場は、以下の通りです。
- 学科+実技コース:15,000円〜25,000円(税込)
- 学科のみコース:8,000円〜15,000円(税込)
学科のみコースは、すでに運転経験がある人や一定の免許を保有している人が対象になることが多く、初めて高所作業車を扱う人は学科+実技コースの受講が一般的です。
相場としては20,000円前後を見込んでおけば大きな差はありませんが、実際には「受講料に何が含まれているか」で総額が変わるため注意が必要です。
受講料に含まれるものと別途費用が必要になるもの
多くの教習機関では、受講料に以下の費用が含まれます。
- 学科講習料(労働安全衛生法令、車両の構造、災害事例など)
- 実技講習料(操作方法、作業前点検、走行・昇降の体験など)
- 教材費(テキスト代)
- 実技に使用する高所作業車の使用料
一方で、次のような項目は別途費用として請求される場合があります。
- 修了証の発行手数料(1,000円〜2,000円程度)
- テキスト代(1,000円〜2,000円程度、受講料に含まれない場合)
- 写真代(証明写真を当日撮影する場合)
- 振込手数料(事前振込指定のある場合)
つまり、「受講料=総額」ではなく、追加で数千円のコストが発生する可能性があることを理解しておきましょう。

学科のみ・学科+実技の費用差について
高所作業車特別教育では、受講者の経験や業務内容に応じてコースが分かれることがあります。
- 未経験者や新入社員 → 学科+実技コース
- 操作体験を通じて安全意識を高めることが目的。
- 費用は15,000〜20,000円程度。
- 操作体験を通じて安全意識を高めることが目的。
- 経験者や特定免許所持者 → 学科のみコース
- 法令知識や災害防止を中心に学ぶ。
- 費用は8,000〜12,000円程度。
- 法令知識や災害防止を中心に学ぶ。
費用差はおよそ10,000円前後ですが、実技を受けておくと作業現場での信頼性が高まります。とくに転職希望者や新規採用者は、学科+実技のフルコースを受けたほうがキャリア形成に有利と言えます。
高所作業車特別教育の受講日数とスケジュール
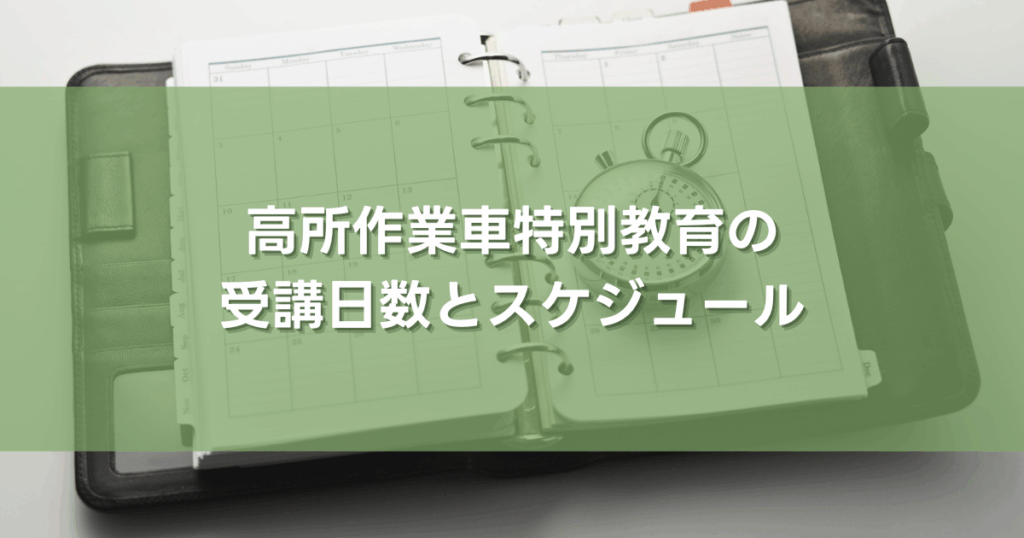
高所作業車特別教育の所要日数は、多くの機関で1〜2日間に設定されています。
- 学科+実技コース:2日間(学科7時間+実技6時間程度)
- 学科のみコース:1日(学科7時間程度)
短期間で修了できるため、業務に支障を出さずに資格取得が可能です。ただし、定員制のため申込締切が早い場合もあり、希望日程がある場合は1か月以上前に予約するのが安心です。
修了証発行料や交通費など見落としがちな追加費用
受講料そのものは相場で10,000〜20,000円程度ですが、実際には次のような「見落としがちな費用」が加算されることがあります。
- 修了証の再発行費用
紛失や破損の際には、再発行手数料(2,000〜3,000円程度)が必要です。 - 交通費・宿泊費
地方在住者が都市部の教習所に通う場合、交通費や宿泊費が大きな割合を占めるケースがあります。 - 安全靴・作業着などの購入費用
教習所から指定される持ち物を新規に揃える場合、数千円〜10,000円程度の出費が発生します。
したがって、「受講料=資格取得の総費用」ではないことを把握しておくことが大切です。申込時には必ず「受講料に含まれるもの・含まれないもの」を確認しましょう。
助成金・補助制度を活用して高所作業車特別教育を受講する
高所作業車特別教育は、条件を満たせば国や自治体の助成金の対象になることがあります。事前に必ず最新情報を確認しましょう。
代表的な制度例
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)
中小企業が従業員に技能講習・特別教育を受けさせた場合、経費の一部が助成されます。
参考:人材開発支援助成金|厚生労働省 - 自治体独自の補助金制度
都道府県や市区町村が、地域の人材育成を目的に補助金を設定しているケースもあります。
いずれも事業主が申請する必要があるため、受講希望者は会社の総務担当や人事担当に事前確認することが必要です。
高所作業車特別教育の受講費用を抑えるための工夫
受講者が個人で費用負担する場合や、会社で複数人を同時に受講させる場合には、以下の工夫でコストを削減できます。
- キャンペーン割引を活用する
教習機関によっては、期間限定で受講料の割引を行うことがあります。 - 他の資格との同時受講
玉掛けやフォークリフトなど、複数の特別教育をまとめて申し込むと「セット割引」が適用される場合があります。 - 地元で受講する
交通費や宿泊費を削減できるため、最終的な総額が大幅に下がります。
特に地方在住の方には、「近隣の教習所で受講する」ことが最も費用対効果の高い選択肢となります。
高所作業車特別教育修了資格取得で得られるメリット
高所作業車特別教育を修了すると、単に「法律上必要な資格を満たす」というだけでなく、キャリア面でも大きなメリットがあります。
- 現場での即戦力化
修了証を持つことで、入社直後から高所作業に従事できるため、企業側にとっても即戦力人材となります。 - 信頼性の向上
安全に作業できる人材として評価され、現場責任者や元請けからの信頼につながります。 - 収入アップの可能性
高所作業車を扱える人材は需要が高く、資格手当や日当アップが期待できます。 - 転職や就職に有利
建設業・電気工事業・通信インフラ関連企業など、多様な分野で活躍できる幅が広がります。
このように、特別教育の修了は「安全性の確保」と「キャリア強化」の両方に直結します。
高所作業車特別教育に関するよくある質問(FAQ)
最後に高所作業車特別教育についてのよくある質問をまとめました。受講の参考になさってください。
Q1. 受講料以外に必ず必要な費用はありますか?
A1. 修了証の発行料や教材費、証明写真代などが別途かかる場合があります。申込時に「受講料に含まれるもの」を必ず確認しましょう。
Q2. 支払い方法は現金のみですか?
A2. 教習機関によっては銀行振込やクレジットカード決済に対応している場合もあります。申込先の案内をご確認ください。
Q3. 会社が費用を負担してくれるケースは多いですか?
A3. 建設業や電気工事業では、安全教育の一環として会社が受講料を全額負担するケースも多いです。個人負担かどうかは勤務先に確認するのが確実です。
Q4. 助成金や補助金を個人で申請できますか?
A4. 原則として事業主が申請主体です。個人受講では対象外となることが多いため、勤務先の総務・人事担当に確認してください。
Q5. 受講をキャンセルした場合、費用は返金されますか?
A5. 教習機関ごとの規定により異なります。キャンセル料や日程変更のルールは事前に必ず確認しましょう。
Q6. 他の資格と同時受講で安くなりますか?
A6. 玉掛けやフォークリフトなどと同時に申し込むと、セット割引を行う教習機関もあります。複数資格を目指す方は確認してみましょう。
Q7. 地方から都市部の教習所に通う場合、交通費や宿泊費は補助されますか?
A7. 原則として公的補助の対象外です。ただし会社が経費扱いしてくれる場合もあるので、勤務先に確認すると安心です。
まとめ
高所作業車特別教育(10m未満)の費用は、一般的に 10,000〜20,000円前後ですが、修了証発行料やテキスト代などの追加コストが発生する可能性があるため、事前に総額を把握しておくことが大切です。
また、助成金制度やキャンペーン割引を活用することで、受講費用の負担を軽減できます。資格を取得することで、現場での即戦力化・信頼性向上・収入アップといったキャリア面のメリットも得られます。
和歌山エリアで受講を検討している方には、小林プラント工業(和歌山技能教習センター)が特におすすめ。地域に根差した安心感と明確な費用設定で、無理なく資格取得を目指せます。
高所作業車を安全に操作するために、そしてキャリアを一歩前進させるために、受講計画をしっかり立てて挑みましょう。

の費用相場と追加コストを賢く把握する方法.png)