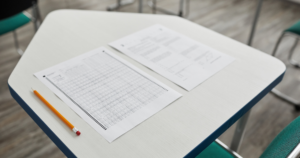移動式クレーン免許を取得したいけれど、
- 年齢や身体条件など、受験資格を満たしているか不安
- 玉掛けや小型移動式クレーン資格が必要なのか気になる
- 試験や講習の流れが複雑でわかりにくい
こうした悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。移動式クレーン免許は建設現場や製造業で必須とされる国家資格ですが、取得条件や申請手続きについて誤解しやすいポイントがあります。この記事では、免許取得のための条件・必要資格・試験内容・書類準備までを整理し、計画的に挑戦できるよう解説します。

移動式クレーン免許とは?

移動式クレーン免許は、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンを運転するために必要となる国家資格です。建設現場や港湾、製造業など、重量物を扱う多くの業務で必須とされる資格であり、取得することで就職やキャリアアップにも直結します。
「移動式クレーン」という名称は、トラッククレーンやラフテレーンクレーン、クローラクレーンなど、自走可能で現場を移動しながら作業できる機械を指します。これらは吊り上げ荷重が大きく、作業の安全性が強く求められるため、免許制度が設けられています。
また、関連資格として「小型移動式クレーン運転技能講習」や「床上運転式クレーン限定免許」などがあり、操作できる機械の範囲が異なります。特に「小型移動式クレーン免許」は、つり上げ荷重5t未満のクレーンに限定されるため、大規模な現場での運用を考える場合は「移動式クレーン運転士免許」の取得が必須となります。
このように、移動式クレーン免許は重量物を安全に取り扱うための基盤となる国家資格であり、関連資格との違いを理解した上で取得を目指すことが重要です。次に、この免許を取得するための基本条件を整理していきましょう。
移動式クレーン免許の取得条件
移動式クレーン免許を取得するには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。
年齢制限と学歴
受験資格は18歳以上であれば満たせます。学歴や職歴による制限はなく、中卒や高卒、社会人経験者でも受験可能です。
身体条件
受験には視力や聴力、色覚といった身体条件が求められます。
□視力:両眼で0.7以上、かつ一眼で0.3以上(矯正可)
□聴力:日常会話が可能であること
□色覚:信号や安全表示の識別が可能であること
身体に障害がある場合でも、補助具の使用や医師の診断書によって受験できる場合があります。
国籍や在留資格
国籍による制限はなく、外国籍の方でも日本の法律に従って受験が可能です。在留カードやパスポートなど、本人確認ができる書類を提出する必要があります。
このように、年齢・身体条件・国籍の3点が基本条件となりますが、これらを満たしていれば幅広い方が受験できる資格です。次は、他資格や実務経験による免除制度について解説します。
必要な資格・経験と免除制度
移動式クレーン免許は、他のクレーン関連資格や実務経験と関わりが深く、場合によっては一部科目の免除を受けられます。
玉掛け技能講習との関係
クレーン作業では「玉掛け」と呼ばれる荷物をフックに掛け外しする作業が不可欠です。そのため、玉掛け技能講習を修了していると、実務上大きなメリットがあります。受験資格に必須ではありませんが、現場での実務を考えると、同時取得を目指す方が多いです。
実務経験による免除
建設現場などで移動式クレーンの補助業務に従事してきた経験がある場合、一部科目の免除が適用されることがあります。ただし、免除には勤務先からの証明書類が必要となるため、事業者証明書の発行を受けてから申請することが求められます。
このように、他資格や経験があると学習負担を軽減できる制度が整っているのが移動式クレーン免許の特徴です。次は、試験の流れと必要な講習について具体的に見ていきましょう。
移動式クレーン免許を取得する試験の流れと必要講習
移動式クレーン免許を取得するには、学科試験と実技試験に合格する必要があります。
学科試験の科目
学科試験は以下の5科目から出題されます。
□ 関係法令(労働安全衛生法やクレーン則)
□ 力学(吊り上げ荷□重・安定計算など)
□ 原動機(エンジンや油圧機構の知識)
□ 電気(クレーン操作に必要な基礎知識)
□ クレーン構造(構造部品や安全装置の知識)
実技試験の内容
実技試験は、実際に移動式クレーンを操作しながら評価されます。主なポイントは以下のとおりです。
- 基本操作(旋回・起伏・走行など)
- 合図に従った安全な荷役作業
- 周囲確認や安全確認の徹底
減点方式で採点され、重大な安全違反があれば即不合格となるため、正確な操作と安全意識が問われます。
試験の実施機関
試験は、公益財団法人安全衛生技術試験協会が全国の安全衛生技術センターで実施しています。試験会場は関東・近畿・九州など各地域にあり、受験者は最寄りのセンターを選んで申請します。
※ここに図解「申込→講習→学科試験→実技試験→免許交付」のフローチャートを挿入すると理解しやすいです。
次は、実際に受験するために必要な書類や手続きについて詳しく解説します。
受験申請と必要書類
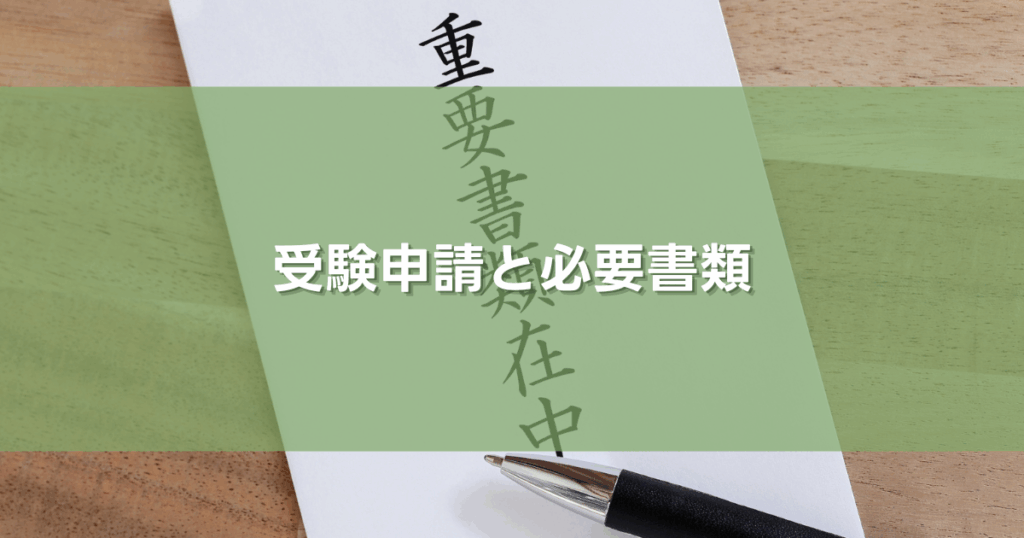
移動式クレーン免許試験を受験するには、決められた書類をそろえて申請する必要があります。申請時の不備は受験できない原因となるため、事前準備が非常に重要です。
申請に必要な書類
□受験申請書(所定の様式)
□証明写真(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影)
□本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
□事業者証明書(免除申請を行う場合に必要)
□医師の診断書(視力や聴力に補助が必要な場合)
提出方法は、郵送または安全衛生技術センター窓口での持参が基本です。オンライン申請は全国で可能で、申込方法は試験センターの公式サイトで確認できます。
受験料と講習費用
受験には費用がかかります。一般的な目安は以下のとおりです。
- 学科試験:6,800円前後
- 実技試験:11,000円前後
- 証明写真代・郵送費:1,000円程度
また、免除制度を利用せずに講習から受講する場合は、技能講習費用が数万円〜十数万円かかるケースもあります。費用は講習機関によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。
申込期限と定員
試験は定員制のため、申し込みは先着順で締め切られる場合があります。受験を希望する方は、試験日程が公開され次第、早めに申し込みを行うことをおすすめします。特に繁忙期はすぐに定員が埋まることがあるため注意が必要です。
次に、受験者がよく抱える疑問や注意点について整理していきます。
移動式クレーン免許の受験についてよくある質問と注意点
移動式クレーン免許の受験を検討する方からは、共通する疑問が多く寄せられます。ここでは代表的な内容を解説します。
未経験でも受験できるのか
未経験者でも受験可能です。ただし、現場経験がないと実技試験で苦戦する場合があります。そのため、技能講習や練習設備が整った教習機関で事前に訓練することが、合格率を高めるポイントです。
健康状態に不安がある場合
視力や聴力に問題がある場合でも、眼鏡・補聴器などの補助具を使用して基準を満たせば受験できます。医師の診断書を提出すれば認められるケースもあるため、まずは相談することが大切です。
外国人技能実習生の受験条件
外国籍の方も受験可能ですが、日本語での学科試験が行われるため、専門用語の理解が必要です。受験前に専門用語集や予想問題集で学習しておくと安心です。
このように、事前の準備と情報収集が、スムーズに受験を進めるカギとなります。最後に記事全体を振り返り、取得条件を正しく理解する重要性をまとめます。

まとめ|条件を理解して計画的に免許取得を目指そう
移動式クレーン免許は、重量物を扱う現場で欠かせない国家資格です。受験には年齢・身体条件・国籍といった基本条件を満たすことが前提となり、他資格や実務経験があれば一部免除も可能です。
学科試験では「関係法令・力学・原動機・電気・クレーン構造」が出題され、実技試験では安全意識と正確な操作が評価されます。申請時には書類の不備がないよう注意し、早めに日程を押さえることが大切です。
資格取得の過程は簡単ではありませんが、条件を正しく理解して計画的に取り組めば、合格は十分に目指せます。
小林プラントでは、移動式クレーンをはじめとする各種技能講習を全国から受け入れています。宿舎を完備し、外国人技能実習生にも対応可能な体制を整えているため、遠方からの受講も安心です。現場で役立つ実践的な指導で、合格と安全な作業をサポートします。



を活かしたステップ-1-300x158.png)